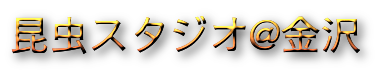百万石蝶談会の嵯峨井氏のお便り。
最近地元のいろんな分野で、「山の色がおかしい、どうなっているんだ」とよく騒がられている。新聞紙上でも何回か取上げられています。ムシヤの諸君は、その理由は何であるかは、ご存知のはず。或る日サガイは久々に近在の倉ケ岳へ入山してみた。頂上近くの池迄は15分から20分で行ける手頃な場所なのですが、最近はご無沙汰してしまっている。
其の道の専門である金沢市職員のM氏にちょっと質問してみた。
—————–
倉ケ岳各地に点在自生する「ミズナラ大木」、殆どが哀れな立枯れ状態。若い幼木は、そうでもないのですが、この状態は今後どのような事態に進展するのでしょうか???林道をポンコツでトボトボ走っていて、思いました。林業のハカセさん、この山の将来像をお聞かせ下さい。また、春ギフシーズンに医王山へは何回か入山していましたが、この様な様子気が付きませんでした。医王山のミズナラもこんな状態なのでしょうかね?17/06/07 (火) M氏からの懇切な回答
—————–
「ミズナラの立ち枯れは、カシノナガキクイムシがナラ菌を媒介して発生します。カシノナガキクイムシは、ミズナラに穿孔しナラ菌を培養し、これが同幼虫のエサになります。このナラ菌によって、ミズナラは枯死に至ります。最近の温暖化で、石川県加賀市から侵入し、金沢市へは倉ヶ岳から侵入しました。侵入4~5年で最大規模に枯れ、それ以後は終息します。大木から枯れ、若木は抵抗力をつけて生き残ります。倉ヶ岳は、今がピークで、これから終息に向かうところかと思います。医王山は、これからピークをむかえるかと思います。ただし、暖地の虫なので、被害は、標高700m程度までかと思います。現在、北上中で、既に富山県にも侵入しています。
—————そして京都在住の蝶友T氏からの私信にも
—————–
ゼフィルス類食樹の立ち枯れは確かに、現在目に余るものが感じられます。滋賀県北部福井県境は数年前から同じ状態で困ったことに、私にはあまり違和感はありませんでした。その為かミズナラ頂芽に産卵依存するアイノミドリは最近殆ど見ていません。替わりにミズナラ若木に依存する種のウスイロオナガシジミあたりが増えている様に思います。
—————–実態として、医王山での2005,2006年のアイノ、ジョウザン、エゾ等のの乱舞が通年に比較して見られない、という現象が確かに感じられた方も多かったでしょう。いつもあれだけの大乱舞が見られた、いわゆるサガイポイントでも、乱舞数が格段に少なかったのは否めませんでした。本当にこの立枯れは今後どの様に変化していくのか、心配な事です。